|
某 ビール工場に見学に行ったとき、意地悪な質問をコンパニオンにしてしまった。 「ここのビールを仕込んでいる水は、何処の水ですかぁ?」 てっきりここの地下水だと思っていた僕の質問にコンパニオンがマイクを握り締めて大声で答えてくれた。 「ハイ!このまちの水道水で仕込んでいます!!」 一瞬。場が静寂になったのは、お判りいただけると思う。素直に回答してくれた、可愛い、一所懸命なコンパニオンにツッコミする気もなくなった。 このまちの水道の水源は自然溢れる山々から湧き出る水であり、その原水は極めて美味いのである。それを敢えてアピールせず、正直に「水道水です!」と(応答マニュアルどおりなのか)答えるのは、逆に正直な会社であると好感を持ったものだ(今はどう説明しているかは、知らないが)。 もっと恵まれない水で仕込んでいるビール工場は、沢山ある(ハズ・・・。 1.仕込んだ米の味がすること であるが、特に仕込み水は日本酒の原料の80%を占める重要な素材である。 水にこだわる蔵は良質の湧き水をタンクローリーで運び、さらに蔵で濾過して使うという、水道料金以上の金を掛けて良い水を確保している蔵もある。 少し専門的な言い回しになってしまったが、とにかく硬度の高い水が良いとされている。 ミネラル成分が多い硬水は、麹菌や酵母菌等の微生物の活性が高くなりアルコール発酵が進みやすいという。一方で硬度の低い軟水は、ゆっくりと微生物が活動するため、時間をかけて穏やかに発酵させることが出来るそうだ。ついでだが、洋食は硬水、和食は軟水で調理した方が美味しいといわれている。水の性質がその国の料理の性質を自ずと規定しているともいえる。 硬水を使い有名なのは「灘の宮水」で、この地域が日本酒の名産地であり現在も大手日本酒メーカーが多い所以である。一般に東日本は硬水、南日本は軟水が多く、軟水は造りづらいといわれているのだが、多くの蔵や関係者の努力により美味い酒が造れるようになったという。自然の恵みと造り手である人とのコラボレーションによって旨い酒は完成されるということであるが、それにしても水の占める重みは大きい。
−ひ で− |
|
|
今宵の隠れ家
きゃりっこ亭
|
国分町のちょっと西の奥、入口に並べられた数々の銘酒の瓶が迎えてくれる。仙台の地酒専門居酒屋の老舗。
恵比寿ビールと日本酒のみを頑なに貫いている。各地の蔵を巡り、作り手の顔が見える酒にこだわりを持ち、特に「十四代」と「東北泉」は、”旬”のラインナップを全て常備している。今や人気酒となった「伯楽星」はデビュー前の「愛宕の松」時代から応援していて、「綿屋」もここが発祥だ。蔵元も良く飲みに来る店である。 一合徳利で出される酒を好みのお猪口に注ぎ手酌で一献。隣同士の客と「これどう思う?」と勧め合って利き酒することも・・・ これも「皆でいろんな酒を味わって欲しい」という店主の心遣いのなせる技か。手作り焼餃子も人気メニューの一つ、日本酒との相性も是非試して欲しい。ついでに自家製レーズンバターもファンが多い。こちらも是非! |
|
今宵の旨酒
東北泉(とうほくいずみ) |
伝説の名杜氏、佐々木勝雄氏が蔵元と造り上げ、その名を冠した「大吟醸 佐々木勝雄」の「うすにごり」は、爽やかな香りの中で米の味を感じさせながら、鳥海山の伏流水の仕込み水の味しか残らないキラキラ輝くお酒でした。
その名杜氏の下で修行し後を継いだ若き神(じん)杜氏もその味をしっかり守りながら、見習い時代も含め全国新酒鑑評会で8年連続金賞受賞という快挙を続けています。
「瑠璃色の海 純米吟醸」も是非! 合資会社 高橋酒造店 山形県飽海郡遊佐町吹浦字一本木57
|
|
2007年10月記 |
|
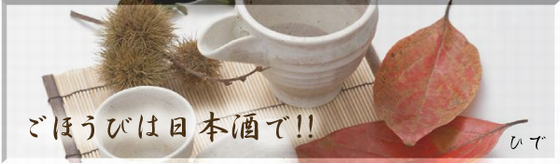
 さて、僕にとって旨い日本酒は、
さて、僕にとって旨い日本酒は、

